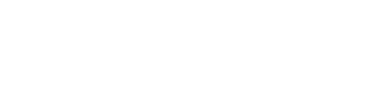広瀬浩二郎著「触常者として生きる」の書評が、産経新聞に掲載されました
2020/09/14国立民族学博物館准教授で全盲の文化人類学者、広瀬浩二郎さんが『触常者とし
て生きる-琵琶を持たない琵琶法師の旅』(伏流社)を刊行した。「触常者」とは、触覚に依拠して暮らす視覚障害者を指す広瀬さんの造語だ。視覚に頼らない生き方を追 体験できる内容となっている。
体験できる内容となっている。
文化人類学の観点から障害を多面的にとらえ、障害の有無にかかわらず楽しめる
博物館のあり方を追求する広瀬さんの15年の研究活動を1冊にまとめた。
「触常者」と、視覚に頼る「見常者」(健常者)とを対にすることで、障害の有
無という区分から離れ、「見えないことはそう悪いことじゃない」という思いを
込めたという。
本書では広瀬さんが各地の博物館で展開する目隠しをして鑑賞物に触れる「無視
覚流鑑賞」のワークショップについて紹介。素早く多くの情報を得られる視覚を
あえて遮断し、触覚に頼りながら彫刻や仏塔のレプリカなどに触れる。素材の質
感など「いつもと違った発見がある。体全体を使うので、目で見たものより記憶
に残りやすい」のが魅力だという。
電灯が普及した明治期以前、人々は夜道を五感を研ぎ澄ませながら歩いた。広瀬
さんは「触覚は誰もが持ち得る感覚であることを本を読んで思い起こしてほしい」
と話す。
広瀬さんは13歳で視力を失い、小学校卒業後に盲学校へ進むと教科書は点字仕
様に。だが、点字を打ちようがない美術は例外だった。つるっとした表紙の手触
りに、視覚的情報を得られない自分を拒絶されたような気がしたという。
一方で美術だけは健常者と同じ教科書。見方を変えれば「目が見える人たちの社
会と盲学校をつなぐ窓(出入口)のようにも感じた」。
窓は、内と外でそれぞれ異なる風景が広がる。本書の表紙と裏表紙には凹凸を効
果的に配し、視覚に頼るか触覚に頼るかで物の見え方が変わることを表現したと
いう。本書が〝2つの社会〟をつなぐ開け放たれた窓のようにも思えてくる。