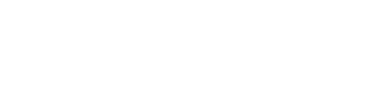ケニー・フリースとドナルド・キーン
2019/03/17
ケニー・フリースは、二度にわたる日本滞在をもとに、“In the Province of the Gods”(小社刊『マイノリティが見た神々の国・日本』)を書き上げた。本書では、身体障害者、LGBT、HIV患者という、トリプル・マイノリティの立場に加え、さらにガイコクジン、しかもユダヤ人(米国)の目から、日本の芸術や文化、日本人の特性について、独特の見地から分析を加えている。著者の視点は、最近のテレビ番組にありがちな自画自賛とは異なり、異邦人の姿勢によって貫かれている。だから、非合理な日本人の習慣や行動に対しては、皮肉を言って釘を刺すことも忘れない。しかし、タイトルのラフカディオ・ハーンの言葉(the Province of the Gods:神々の国)が示すように、熱烈な日本ファンであることには変わりない。
そして、著者の発言の中に、日本人の眼差しは自分にとって居心地が良い、というものがある。その理由の一つとして、「日本神話の中に障害をもつ神がいることと関係があるのではないか」という指摘を行っている。これについては、異論があることは十分承知している。例えば、日本人にはもとより欧米コンプレックスがあり、特に戦争で負けたアメリカ人にはその傾向が強いため、単にエリート層のアメリカ人に対して卑屈に振る舞っているのを、優しく接してくれたと勘違いしただけではないのか。また、昨今のME TOO運動が日本で広まらなかったことからもわかるように、日本において少数者に対する差別意識が少ないなどというのはとんでもない誤解であり幻想である。日本人の人権感覚の乏しさに思いが至らない著者の目は節穴ではないか。そういった批判の声が聞こえて来そうである。確かに、有色人種でしかも貧困層のマイノリティが来日した場合、同様の感想を持ち得たかと言われれば自信がない。だからといって、著者の日本に対する印象が全くの根も葉もないデタラメかと言えば、それもまた違うと思うのである。
例えば、先日、日本文学の価値を世界に発信してくれたドナルド・キーン氏が他界した。そして、キーン氏もまた、ゲイでありユダヤ人という、ダブル・マイノリティであったのである。キーン氏の場合、長らく差別に苦しんだ経験を持つとも言われる。そのキーン氏が初めて日本文学と接するのは、アーサー・ウェイリー訳の『源氏物語』によってである。その後、米軍の通訳として来日し、文学や芸術に関する造詣を深め、川端康成や三島由起夫をノーベル賞委員会に推したのもキーン氏であった。かといってキーン氏の関心が、きらびやかな王朝文化に代表される日本人の美意識にのみ向けられていたわけではない。例えば、キーン氏は2011年に日本に帰化するが、これは東日本大震災で被災した人々が黙々と作業する姿が、高見順の『敗戦日記』に描かれた終戦直後の人々と重なり、日本人に対する愛おしさが一気に込み上げてきたからだと言う。またある講演で、日本で一番感動したことはという質問に対して、「走る郵便配達員」と答えている。キーン氏の日本への思い入れは、愚痴を言わずただ黙々と働く勤勉で実直な人々に対してであったのである。
キーン氏ばかりではない。ロバート・キャンベル氏(日本文学)も、ゲイであることを昨年公表している。また、日本文学の先駆者であるラフカディオ・ハーンも若い頃、片目を失い隻眼であった。ラフカディオ・ハーン、ドナルド・キーン、ロバート・キャンベルといった日本文学に傾倒した三人の碩学が、いずれもマイノリティであったという事実は、単なる偶然であろうか。日本文学の中には、マイノリティを引きつける何かがあるのではないかという仮説は十分熟考に値すると、私は考えている。
ここで再び、日本神話の中に障害をもつ神がいるというケニー・フリースの指摘に立ち戻りたい。障害をもつ神とはヒルコのことであり、ヒルコは、古事記と日本書紀の国生みのところで登場する。まず、該当する古事記の箇所をひもといてみよう。
「ここにイザナギの命のりたまわく、『しからば吾と汝とこの天の御柱を行き巡り逢ひて、みとのまぐはひせむ』とのりたまひき。かくちぎりてすなわち、『汝は右より巡り逢へ。我は左より巡り逢はむ』とのりたまひ、ちぎりおえて巡る時、イザナミの命先に『あなにやし、えをとこを』と言ひ、後にイザナギ命、『あなにやし、えをとめを』と言ひ、各々言ひおへし後、その妹に告げて、『女人先に言へるは良からず』とのりたまひき。しかれどもくみどにおこして、子水蛭子(ヒルコ)を生みき。この子は葦船に入れて流し去てき」
つまり、イザナギとイザナミのみとのまぐわい(聖婚)の中で、女神であるイザナミが、男神であるイザナギより先に、「あなにやし、えをとこを」(あら、ハンサムね)と言ったことによって、ヒルコという障害児が生まれてしまったというのである。そして、ヒルコは葦船に入れられて、海に流されてしまった。
ついでに、日本書紀の方も眺めてみよう。
「そこで天の柱を回ろうとし約束していわれるのに、『あなたは左から回りなさい。私は右から回ろう』と。そこで分かれめぐって行きあった。女神が先に唱えていわれるのに『おや、なんとすばらしい男の方ね』と。男神が後から答えていわれ、『おや、なんとすばらしいおとめだろう』と。ついに夫婦の交りをして、まず蛭児(不具の子)が生まれた。そこで葦船にのせて流してやった」(講談社学術文庫 『日本書記(上)全現代語訳』)
どちらからも、女が前に出て出しゃばるとろくなことはない、といった寓意が読み取れる。ヒルコをめぐる記紀のエピソードは、マイノリティに優しいどころか、女性差別と障害者差別を合わせたようなものだったのである。
両者の違いとして、日本書紀においてこの逸話は本編にはなく、「一書にいう」という別伝の形で紹介されている点がある。また、古事記では、ヒルコが「水蛭子」、日本書紀では「蛭児」と表記されている点でも違いが見られる。前者が骨のないクラゲのような赤子(すなわち、障害児)を連想させるのに対し、後者は、血を吸う山蛭、すなわち人間に害なす存在としてイメージされる。
ところが、葦船で流されたヒルコは、その後、摂津国・西宮に流れ着く。そして、西宮の住民・夷三郎に拾われ、大切に育てられるのである。ヒルコは、西宮神社の祭神・夷(エビス)として祭られ、商売繁盛の神、海の守護神として、特に商人たちの間で広まっていく。エビス信仰はさらに、えびす講、えべっさんとして親しまれ、商人だけでなく農民まで巻き込んで、絶大な人気を博するようになるのである。このような後日談は、記紀や公式の歴史文書に書かれたものではない。それでは、どうやって伝えられたかと言えば、民間伝承によってなのである。
しかしこれは、非常に重要な点かと思われる。つまり、公式の歴史書では排斥された記紀のアウトサイダーを庶民たちが復活させ、新たなヒーローに仕立て上げたことになるからである。さらに、エビス(夷)という言葉にも注目したい。エビスは「蝦夷」と書くこともある。蝦夷は「えみし」とも読み、大和朝廷によって滅ぼされた東北の被征服民のことをさす。また、東夷(あずまえびす)と言うように、夷(えびす)とは都から見た野蛮人の総称であり蔑称でもある。いずれにせよ、エビスの背後には、マイノリティの影が見え隠れするのである。
さらに話を広げていきたい。これもつい最近のことであるが、哲学者の梅原猛氏が逝去された。梅原氏は膨大な著作を残したが、氏が一番思いを寄せていたのは非業の最期を遂げた歴史上の人物についてである。それは例えば、大国主命、聖徳太子、柿本人麻呂であり、彼らについてはそれぞれ大著を書き上げている。例えば、『神々の流竄』においては、古事記の国譲りの記述は、大国主命の一族が大和から出雲に追放されたことを暗示しているのだとし、『隠された十字架』では、聖徳太子の子、山背大兄王は蘇我入鹿によって一族惨殺されるが、法隆寺は太子一族の慰霊のために建立された寺であるとする。また、『水底の歌』では、柿本人麻呂は流刑に処せられ、その地で不遇のまま生涯を終えたとしている。これらの人々は当然恨みを飲んで命を絶たれたわけであるが、一方、権力者(梅原氏によれば主として藤原氏)からしてみれば、彼らが怨霊となって自らに祟ることを恐れおののいていたのではないか、というのだ。そして、祟りを免れるため、壮大な社殿を建立したり、神として祀ったのではないか。このことが、日本の宗教、とりわけ神道の形成過程に多大な影響を及ぼすこととなる。神道において、最も重要な宗教儀式である祭りの意義は、荒魂(あらみたま)を和魂(にぎみたま)に転化させ、神々の怒りを鎮めることにあるとされている。このような慰謝・慰霊を、儀式の根幹に据えたことこそが、日本宗教の一大特色をなしていくのだ。このような例は、菅原道真(天神様)、平将門、崇徳上皇などにも見られる。
権力者の中には、加害者の一族や子孫が多くいるため、祟りが自分の身に及ばないようにするため、慰霊の儀式を率先して行ったり、寺社を建立したりした。しかし、非業の死を遂げた人を神として祀る信仰は、やがて民衆の間にも広がりを見せ、信者たちをどんどん増やしていく。しかし、民衆がマイノリティの神々を崇拝した理由は、権力者の場合とは異なり、マイノリティの神のモデルとなった歴史上の人物に対して、同情や哀惜の念を抱いたためであったはずだ。また一方では、彼らを不幸な境遇に貶めた権力者に対して反感を募らせ、体制批判的な思いも含まれていたに違いない。このような庶民感情を表すものとして、私は「贔屓」という言葉を用いたい。「判官贔屓」、「太閤贔屓」(秀吉は権力者であったが、これが流行ったのは江戸時代である)がまさしくそうである。そして、記紀で抹殺された神、ヒルコが福の神・エビスとして復活を遂げた背景には、このような「贔屓」の大衆心理が蠢いていたのではないか。ちなみ、エビスは事代主(コトシロヌシ)とも同視される。事代主は大国主命の子であり、国譲りにおいて天孫族(ニニギ)に対して消極的抵抗を行った神である。また、大国主命は大黒天とも同一視され、これまた庶民から愛される神であり、エビスと大黒天は二福神として親しまれている。ここにおいて、ヒルコ、エビス、事代主、大国主命という、反大和系の神々が一本の線によって結ばれる。ヒルコはもちろん歴史上の人物ではないが、『神々の流竄』において梅原氏が指摘した点からすれば、大和朝廷によって抹殺された一族ないしはその王という見方も十分成り立つであろう。
奈良時代に権力者のエゴイスティックな動機によってもたらされた日本宗教の特色は、やがて庶民によって「贔屓」の大衆心理へと質的変貌を遂げ、千年以上の熟成期間を経て、文化の深層に澱のように溜まっていく。そして、それは日本人の風俗や信仰、言語感覚、行動様式に対して深く影響を与えていったのであろう。そして、このような深層の感情を掬い上げ、言葉にしていくのが、まさに文学の重要な役割に他ならないのだ。
ラフカディオ・ハーンは、日本の化け物に関する伝承の中に、マイノリティの悲哀を感じ取っていたに違いない。そして、このような観点は、水木しげるの妖怪や円谷映画の怪獣の中にも受け継がれている。ドナルド・キーン氏やロバート・キャンベル氏については、解説できるほど著作にふれていないが、やはり同様の事情があったと想像されるのだ。キーン氏は、自らのマイノリティ性について多くを語っていないが、公民権運動以前に青年期を過ごしたキーン氏にとって、それをあからさまにし権利拡張運動に邁進するには抵抗があり、文学的空間の中にひっそりと自分の居場所を求めることを良しとしたのではないか。これはけして責められることではないし、これからもマイノリティの生き方の選択肢として、尊重されるべきであろう。
ここで一つ考えておきたいのは、三者が心酔した日本文学と現代作家の多くの作品との間には溝があるのではないか、ということである。ラフカディオ・ハーンはいわずもがなであるが、キーン氏にせよキャンベル氏にせよ、主として関心を寄せているのは古典作品に対してである。例えば、村上春樹のようにノーベル賞候補にまでなって、世界文学と称される作品の中に、マイノリティを引きつける伝統の余韻が残されているのであろうか。この点は、非常に気にかかるところである。私は、最近の作家たちの作品をあまり読んでいないので、憶測の域を出ないが、正直なところ悲観的である。
ハーンは、近代化の波によって、日本の古き良き伝統が失われることについて強い危惧を抱いていたが、それが今や、文化の深層にまで達しようとしているのではないのか。そして、贔屓の感情の衰退が文化の深層にまで及び、完全に失われることになれば、それは深層の福祉の喪失にもつながるのではないか。それがたとえ人権に置き換わったとしても、権利だけでは望ましい社会はけして築かれないのではないか。ケニー・フリースが合理主義や人権思想が張り巡らされたアメリカ社会にいる時よりも、日本にいる時の方が心地よく感じられた理由も、この辺にあるのではないか。
長きにわたり日本文化の通奏低音をなしていた庶民感情の基層が損なわれることのなきよう、心より祈るばかりである。